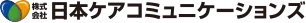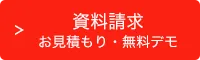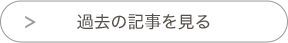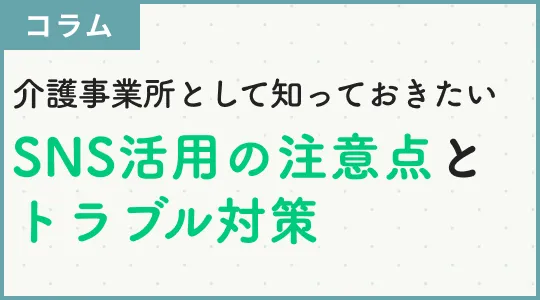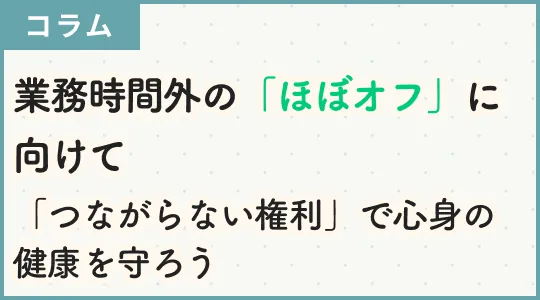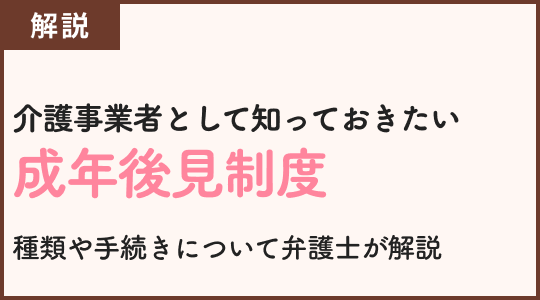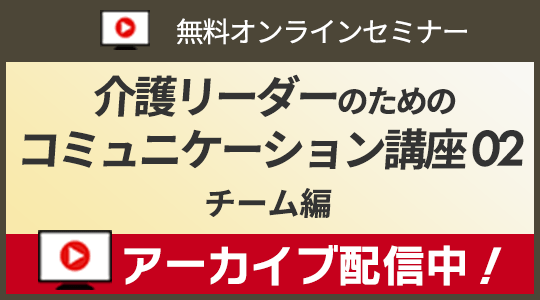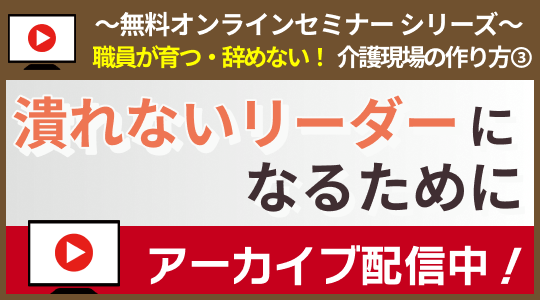執筆者:雨宮紫苑
わたしがはじめて「社会福祉」なるものに触れたのは、小学5年生のときだった。総合の授業の一環で、老人ホームを訪問することになったのだ。
小学校から坂を下ったところにある、比較的新しい施設だったと思う。
まだ10歳だったわたしは、老人ホームがなにかすらよくわかっていなかった。おじいちゃんおばあちゃんが暮らしているらしい、くらいの認識だ。
しかしそこで出会った介護士さんのことを、20年以上経った今でも、鮮明に覚えている。
総合の授業で初めて訪れた老人ホーム
先生に引率されながら、クラスのみんなと老人ホームに到着。白い壁と、明るい木目の床が印象的だった。
案内されたのはリビング兼食堂と思われる大き目の部屋で、20人くらいのおじいちゃんとおばあちゃんが迎えてくれた。
ほとんどが車椅子に乗り、それぞれ違う色のひざ掛けを使っている。
小さなキッチンのとなりに大きなテーブルと多くのイスがあり、その奥にはいくつかのソファイス。
普段自分の家で見ているよりも数倍大きいテレビの音に驚いた。
そこでなにをしたかは、正直あんまり覚えていない。
ただ先生に、「お年寄りと雑談しなさい」と言われて困惑した記憶はある。いったいなにを話せばいいのやら……。
そばにいたおばあちゃんに適当に学校の話をしたところ、耳が遠いのか、いまいち伝わらない。
わたしはわたしでおばあちゃんが言っていることを聞き取れず、うまく会話ができない。
それでもおばあちゃんは始終うなずいて、「いい子だねぇいい子だねぇ」と優しく微笑んでくれた。
学校への帰り道、みんなで坂を登りながら、わたしは祖父母を思い出す。
当時はまだ母方の祖父母、父方の祖母が生きていた。
母方のおじいちゃんは病気で杖をついていたけど、おばあちゃんは裁縫が得意で布を持っていけば服を作ってくれるし、父方の祖母は近場に住んでいたのでよくおいしいご飯を用意してくれる。
いまは元気だけど、おじいちゃんおばあちゃんもいつか、こういう場所で暮らすときが来るのかな……?
施設はきれいだし、ご飯もおいしい。でも毎日家族と会えるわけではないし、毎日お出かけできるわけでもない。それはちょっと、さみしいんじゃないだろうか。
帰り際、おじいちゃんおばあちゃんが口々に「また来てね」と言ってくれたから、子どもだったわたしはそれを聞いて、素直に「じゃあまた来よう」と思った。それで喜んでくれるなら、と。
劇を披露するためふたたび老人ホームへ
とはいえ、ただもう一度訪問するだけではおもしろくない。
そうだ、劇をしよう!
劇なら、少人数で訪問しても、多くのおじいちゃんおばあちゃんに楽しんでもらえるはず。
そういったことに興味がありそうなクラスメイトを5人ほど誘って、グループを「吟遊会」と名づけた。
当時読んでいた漫画に出てきた単語をかっこいいから使っただけで、とくに意味はない。
この思いつきを両親や先生に相談するとすごく褒めてもらったので、意気揚々と劇の台本を書き始めた。
あまり覚えていないけど、風の精霊を呼び起こして勇者がなにかを倒す系の話だったと思う。これまた、読んでいた漫画の影響だ。
昼休みや放課後、吟遊会のメンバーで集まって練習スタート。舞台監督さながら、「もっと感情をこめて!」「しゃがんでみよう!」なんて指示を飛ばす。
わたしは「自分が書いた物語を披露する」という状況に、完全に酔っていた。
ひとしきり練習し終え、緊張しながら老人ホームに電話する。手元には、親とともに考えた訪問依頼のセリフのカンペ。
劇を披露するため訪問のお願いをすると、「ぜひぜひ!」と即答してくれた。
所詮は子どもの思いつき、劇のクオリティは……
約束の日、吟遊会の6人で老人ホームを訪れた。
先生はいないので、対応はすべてリーダーのわたしの仕事。緊張しつつも、ちゃんと自己紹介をして、受け入れのお礼も伝える。
前回と同じ食堂に行くと、20人近いおじいちゃんおばあちゃんがいて、再び満面の笑みで出迎えてくれた。
劇がよく見えるように、という配慮だろう。テーブルはどかされ、おじいちゃんおばあちゃんは車椅子に乗り、正面を囲うように半円にきれいに並んでいた。その後ろには、カラフルなエプロンを着た介護士さんが3人。
よーし、わたしが監督の劇をみんなに披露だ!と、意気込んだものの。
……いやもう、思い出すだけで恥ずかしい。もはや思い出したくない。
ド素人の小学生の頭の中には「舞台セット」やら「衣装」なんて発想がなく、TシャツにGパンで風の精霊を演じた。演じながら、「さすがにTシャツは変じゃない?」と気付く。
いま思うと不思議だが、実際に披露するまでそういったことにまったく意識がいかなかったのだ。そもそも手ぶらで劇を披露という時点で、おかしいと気付くべきだった。せめて杖とかさ……。
唯一持ち込んだのは、小さなコンポ。小学生でも持てるくらいのサイズで、MDに録音した音楽を流すために持っていった。
のだが、家庭用なので音量が小さく、音楽や効果音はわたしですらほとんど聞こえなかった。おじいちゃんおばあちゃんには、まったく聞こえていなかっただろう。
終わった後我に返って思ったのだが、そもそもストーリーが全然おもしろくない。ジャンプ漫画に影響された薄っぺらいオリジナル冒険譚をやるくらいなら、おとなしく桃太郎でもやっとけばよかった。
ああ、恥ずかしい。人様にお見せできるようなものではなかった。
「来てくれてありがとう」と泣いたおばあちゃん
やらかした自覚はあったので、「これじゃさすがに喜んでもらえないだろうな……」と落ち込んだし、協力してくれた介護士さん、退屈な時間を強いられたおじいちゃんおばあちゃんに対して、申し訳なさでいっぱいだった。
エンディングを迎えお辞儀をし、おそるおそる顔を上げる。
怒られたりしないかな……と思っていたわたしの目に、衝撃的な光景が飛び込んできた。
なんと、何人ものおばあちゃんが泣いていたのだ!
えぇ!? こんなしょうもない劇で!? なんで!?
介護士さんに「せっかくならお話して行ってください」と言われたので、目の前の泣いているおばあちゃんの前でかがみ、「見てくれてありがとうございました」と伝えた。
するとおばあちゃんは宝物を握りしめるように両手でわたしの手を取り、「来てくれてありがとねぇ。孫を思い出したよ」とさらに涙を流し始めた。
突然手を握られてびっくりしたが、それよりも驚いたのはその手の冷たさだ。まるで雪の中何時間も外にいたような温度だった。その温度を感じ、おばあちゃんの手をさすりながら、なんだかわたしも泣きそうになる。
「いい劇をしよう」と思っていたけどそんなのは必要なくて、ただ「一緒にいる」だけでよかったのだ。
帰り際、介護士さんは「放課後に寄ってくれるだけでもいいから、またいつでも来てね」と何度も言ってくれた。「今日はありがとう」とも。

入居者の幸せを願う介護士
そのときは深く考えず、「いいことしたなぁ~」という充実感とともに帰宅した。おじいちゃんおばあちゃんが喜んでくれてよかった、と。
でも大人になって改めて思うと、介護士さんにとってわたしたちの訪問は、とんでもなく面倒だったと思う。
ただでさえ介護士は大変な仕事なのに、子どものお遊戯に付き合うためにテーブルをどかして、おじいちゃんおばあちゃんを食堂に集めて、その時間に合わせて仕事の手を止めて……。面倒くせぇ!
わたしだったらイヤだよそんなの! しかも肝心の劇はとんでもなくつまらないし! 風の精霊ならせめて白い布でも巻いてこいよ!
それでも介護士さんたちは、しょうもない劇を披露する世間知らずな小学生を笑顔で受け入れ、「また来てね」とまで言ってくれたのだ。
それはきっと、わたしたちの訪問が、おじいちゃんおばあちゃんにとってどれだけ嬉しいことかを知っていたからだろう。それこそ、セリフや音楽が聞こえなくても泣き出してしまうくらいに。
老人ホームの中に入るのは、自分自身が高齢者になるか、身内が入居するときくらいなもの。老人ホームの中がどうなっているのか、日々どんな暮らしが営まれているか、知らない人は多いと思う。
それでも今この瞬間も、おじいちゃんおばあちゃんが幸せに暮らせるよう、汗水たらして働いてくれている人がいるのだ。20年前に出会った介護士さんたちは、それを教えてくれた。
ちなみに山口県に住んでいる裁縫が得意な祖母は、数年前から老人ホームに入っている。
わたしはドイツに住んでいるのでなかなか会いに行くことはできないが、優しい介護士さんに囲まれ、穏やかに暮らしているという。

雨宮 紫苑
ドイツ在住フリーライター。Yahoo!ニュースや東洋経済オンライン、現代ビジネス、ハフィントンポストなどに寄稿。著書に『日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち』(新潮新書)がある。