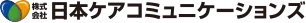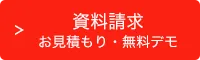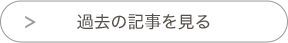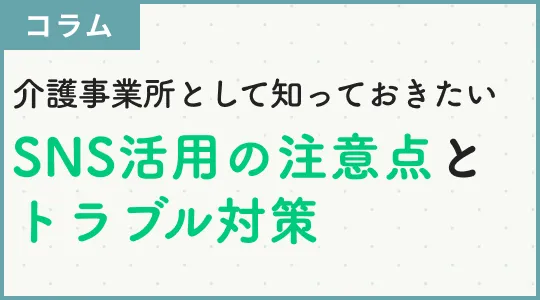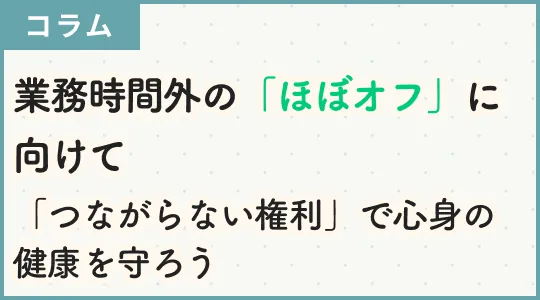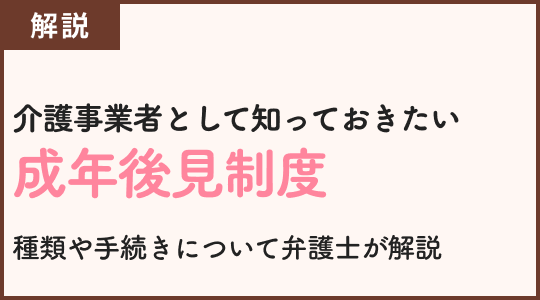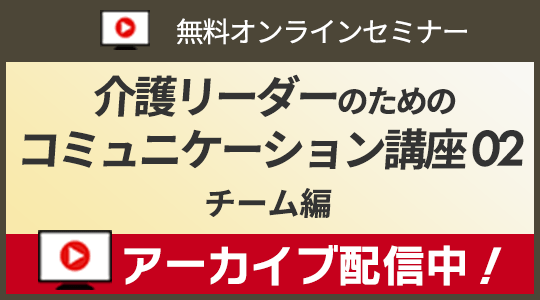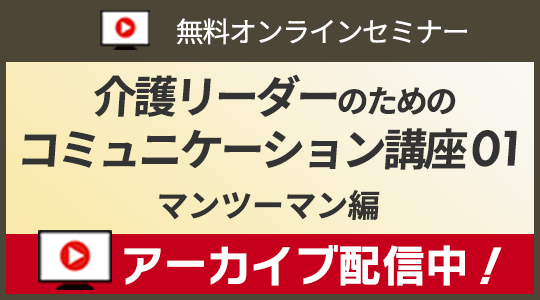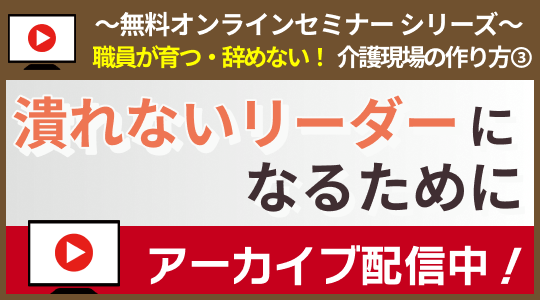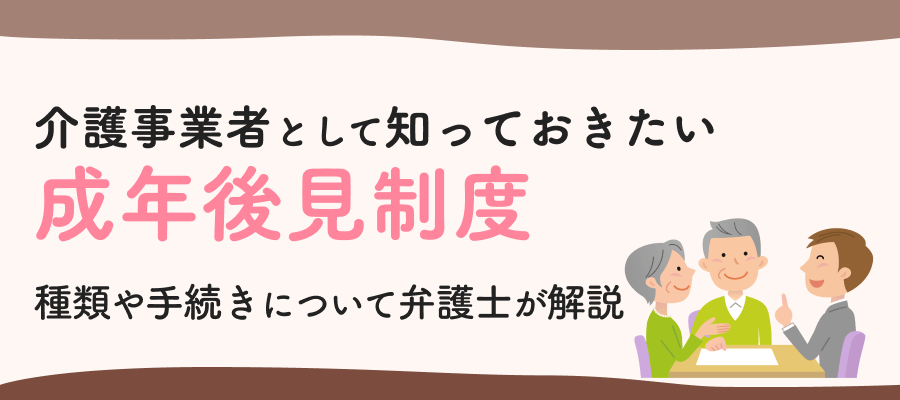
「成年後見制度」は、認知症などによって判断能力が低下した人のための制度です。介護事業者は高齢者を受け入れるケースが多いため、成年後見制度について正しく理解しておきましょう。
本記事では、介護事業者が知っておきたい成年後見制度の基礎知識を解説します。
– 目次 –
成年後見制度とは
「成年後見制度」とは、判断能力が低下した人が契約の締結などを行う際、後見人等がサポートをする制度です。
認知症などによって判断能力が低下すると、自分にとって必要なものやメリットがあるものと、そうでないものの区別が難しくなります。詐欺や悪徳商法に騙されてしまうリスクも高くなります。
成年後見制度を利用している場合、後見人等が本人による意思決定に対して同意を与える、本人に代わって契約を締結するなどのサポートを行います。
後見人等のチェックが入ることにより、不必要な契約を締結するなど、本人にとって不利益な事態を防ぐことができます。
成年後見制度の種類
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に大別されます。
法定後見制度は、さらに「成年後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれています。
法定後見制度|成年後見・保佐・補助
「法定後見制度」は、法律によって内容が細かく決められた成年後見制度です。家庭裁判所の審判によって利用が開始されます。
法定後見制度には「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
|
成年後見 |
保佐 |
補助 |
|
|---|---|---|---|
|
要件 |
判断能力を欠く常況にある | 判断能力が著しく不十分である | 判断能力が不十分である |
| 代理権 (契約の締結などを本人に代わって行う権利) |
◎ |
△ |
△ ※家庭裁判所の審判で定められた法律行為のみ |
| 同意権 (本人の意思表示に対して同意を与える権利) |
- ※代理権があるため不要 |
○ ※民法13条1項に定められた行為+家庭裁判所の審判で定められた行為 |
△ |
| 取消権 (本人の行為を取り消す権利) |
◎ ※日常生活に関するもの以外の行為全般 |
○ ※民法13条1項に定められた行為+家庭裁判所の審判で定められた行為 |
△ |
本人の判断能力の低下が最も著しいのが成年後見、最も軽微なのが補助で、保佐はその中間です。判断能力の程度に応じて、後見人等の権限に差が設けられています。
法定後見の場合、後見人等は家庭裁判所が選任します。本人などが後見人等を推薦することはできますが、そのとおりに選ばれるとは限りません。
任意後見制度
「任意後見制度」は、当事者が内容を自由に決められる成年後見制度です。本人と任意後見受任者(=任意後見人になる人)が締結する契約にしたがって、任意後見の内容が決まります。
任意後見の大きな特徴は、本人が任意後見受任者を選べる点や、その権限の範囲を自由に決められる点です。
また、判断能力が低下してから申し立てる法定後見とは異なり、任意後見は判断能力が十分残った段階で契約を締結します。そのため任意後見は、認知症対策としても広く活用されています。
成年後見制度を利用する際の手続き
法定後見制度の手続き|家庭裁判所に対する審判の申立て
法定後見制度である成年後見・保佐・補助を開始するためには、家庭裁判所に対して開始の審判を申し立てる必要があります。
家庭裁判所は、本人の判断能力の状態などを審査し、要件を満たしていると判断した場合には開始の審判を行います。その際、成年後見人・保佐人・補助人が選任されます。
家庭裁判所の審判が確定すると、成年後見人・保佐人・補助人は職務を開始し、本人のために契約の締結などをサポートします。
任意後見制度の手続き|任意後見契約の締結など
任意後見制度を利用する場合は、本人の判断能力が十分である状態で「任意後見契約」を締結する必要があります。
任意後見契約は、本人と任意後見受任者の間で公正証書によって締結します。将来的に本人の判断能力が低下した際、任意後見人が行うべき職務の内容や、代理権の範囲などを定めます。
任意後見契約の締結後、本人の判断能力が不十分となった場合に、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人は、任意後見人が職務を適正に行っているかどうかを監督する人です。
任意後見監督人が選任された時点で、任意後見受任者は任意後見人となり、その職務を開始します。
任意後見人は、任意後見契約に従って、本人のために契約締結などの代理権を行使します。
介護事業者が認知症患者などを受け入れる場合の注意点
介護事業者が受け入れる利用者の中には、認知症などによって判断能力が低下した人も含まれています。
利用者が成年後見の対象となっていることを見落とすと、後に深刻なトラブルが発生してしまいかねません。そうならないように、利用契約を締結する際には以下のポイントに注意しましょう。
- 後見等の有無や種類を確認する
- 成年後見人等の同意を書面で取得する
後見等の有無や種類を確認する
介護事業者が利用の申込みを受ける際には、利用者に対して後見等の有無や種類を必ず確認しましょう。
本人からの申告内容を明確化するため、紙に書いてもらうなどして記録化することが大切です。
成年後見人等の同意を書面で取得する
後見等の種類によって、本人が単独でできることと、後見人等の同意が必要なことの範囲が異なります。介護施設の利用に関しては、下表のとおり整理されます。
|
後見等の種類 |
介護施設の利用に関する取り扱い |
|---|---|
|
成年後見 |
後見人が本人を代理して契約を締結する(本人による契約の締結は不可)。 |
|
保佐 |
原則として本人が契約を締結し、保佐人の同意を得る。 |
|
補助 |
本人が契約を締結する。家庭裁判所の審判によって同意が必要とされている場合に限り、補助人の同意が必要。 |
|
任意後見 |
代理権の範囲内であれば、本人も任意後見人も契約を締結できる。 |
成年後見の場合は、後見人に代理で契約に調印してもらう必要があります。
保佐と補助の場合は、契約書には本人に調印してもらったうえで、保佐人と補助人の同意を得るのが確実です。
任意後見の対象者本人が契約を締結するときは、本人の判断能力が十分あるかどうかを観察しましょう。少しでも疑念がある場合は、本人ではなく任意後見人による契約の締結を求めるべきです(代理権の範囲内である場合に限ります)。
法律上のルールは複雑ですが、トラブルを避けるためには、保守的な運用をすることをお勧めします。
阿部 由羅
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。
注力分野はベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続など。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
各種webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw