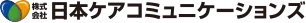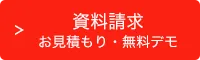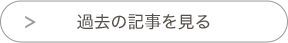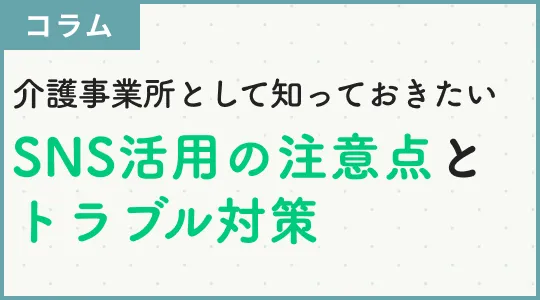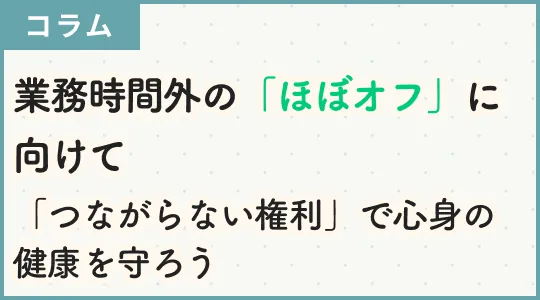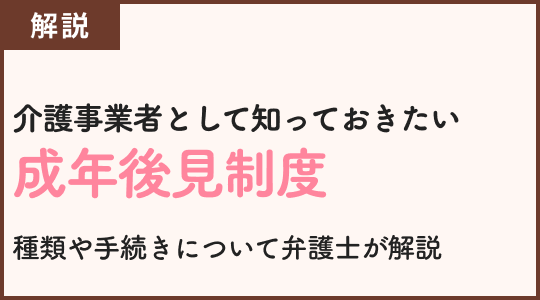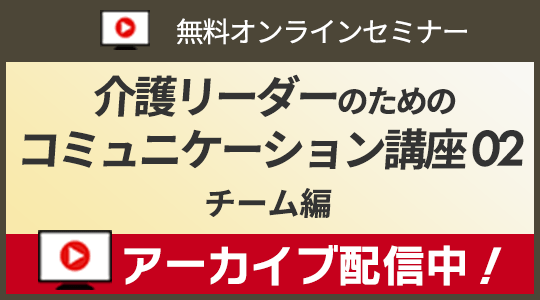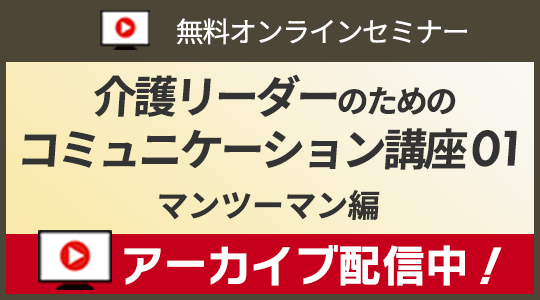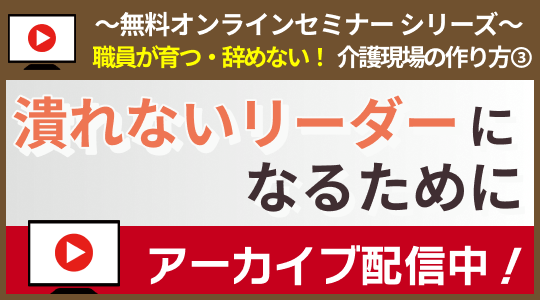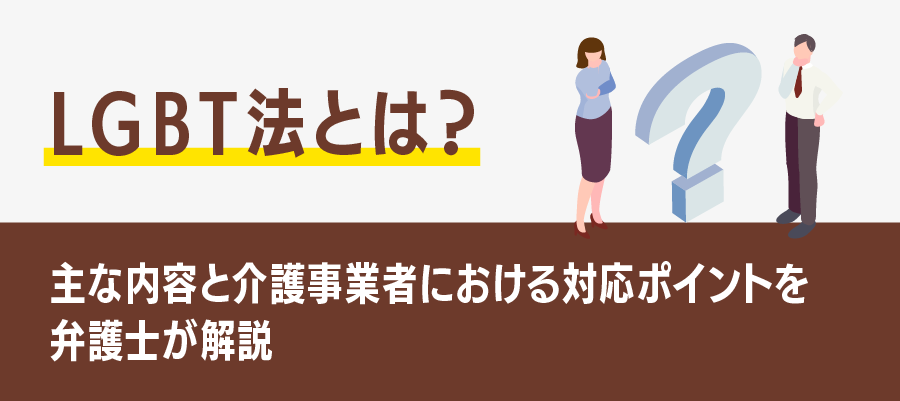
執筆者:阿部 由羅(ゆら総合法律事務所・代表弁護士)
LGBT法*1は、「LGBTQ」と呼ばれる性的マイノリティに対して寛容な社会を実現するために制定された法律です。
介護事業者においても、LGBT法や男女雇用機会均等法を踏まえて、雇用するLGBTQに対する差別の防止などに取り組む必要があります。
本記事ではLGBT法の概要や、LGBTQを雇用する介護事業者が講ずべきセクハラ防止措置などについて解説します。
LGBT法とは
LGBT法とは、性的指向およびジェンダーアイデンティティ(性自認)の多様性を受け入れる精神を涵養し、その多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする法律です。
LGBTQとは
「LGBTQ」とは、性的マイノリティ全般を意味する略称です。
レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー・クエスチョニング(またはクィア)の頭文字に由来しています。
| レズビアン(Lesbian) | 女性を恋愛対象とする女性 |
| ゲイ(Gay) | 男性を恋愛対象とする男性 |
| バイセクシュアル(Bi-Sexual) | 両性を恋愛対象とする人 |
| トランスジェンダー(Transgender) | 生物学的性とジェンダーアイデンティティが一致していない人 |
| クエスチョニング(Questioning) | 性的指向やジェンダーアイデンティティが定まっていない人 |
| クィア(Queer) | レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーに当てはまらない性的マイノリティ |
LGBT法の基本理念
LGBT法の基本理念は、すべての国民がその性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるべきというものです(同法3条)。
LGBTQに対する不当な差別をなくし、国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、国・地方公共団体の役割や事業主の努力義務などが定められています。
性的指向とジェンダーアイデンティティ(性自認)
LGBT法では、性的指向とジェンダーアイデンティティ(性自認)が以下のとおり定義されています(同法2条)。
ジェンダーアイデンティティ(性自認):自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無または程度に係る意識
簡単に言えば、性愛の対象として誰を好きになるかが「性的指向」、自分の性別を何だと認識しているかが「ジェンダーアイデンティティ」です。
LGBTQの性的指向とジェンダーアイデンティティは、おおむね以下のように整理されますが、そのあり方は人それぞれ多様であることに留意する必要があります。
| 性的指向 | 性自認 | |
|---|---|---|
| レズビアン(Lesbian) | 女性 | 女性 |
| ゲイ(Gay) | 男性 | 男性 |
| バイセクシュアル(Bi-Sexual) | 男性・女性両方 | 人それぞれ |
| トランスジェンダー(Transgender) | 人それぞれ | 生物学的性と異なる性 |
| クエスチョニング(Questioning) | 人それぞれ | 人それぞれ |
| クィア(Queer) | 人それぞれ | 人それぞれ |
LGBT法に基づく事業主の努力義務|介護事業者がとるべき対応
事業主には、前述のLGBT法の基本理念にのっとり、以下の努力義務が課されています(同法6条1項)。
(2)国または地方公共団体が実施する、性的指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解増進の施策に協力する。
介護事業者においても、LGBTQへの理解を促すための研修を実施する、LGBTQ当事者である従業員のための相談窓口を設けるなどして、上記の努力義務を果たすことが求められます。
介護事業者がLGBT法に基づく努力義務を果たしていなくても、特にペナルティはありません。
しかし後述するように、男女雇用機会均等法*2との関係ではペナルティの対象になり得ます。また、社内におけるLGBTQへの差別が露見すれば、介護事業者としての評判が低下するおそれがあるので注意が必要です。
介護事業者がLGBTQを雇用する際には、男女雇用機会均等法にも要注意
LGBTQを雇用する介護事業者においては、LGBT法だけでなく、男女雇用機会均等法の規制にも対応する必要があります。
LGBTQに対する差別はセクハラに当たる
男女雇用機会均等法では、事業主に対して、職場におけるセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)を防止するため、雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けています(同法11条1項)。
厚生労働省が公表しているセクハラ防止指針では、職場におけるセクハラには同性に対するものも含まれるほか、被害者の性的指向または性自認は問わない旨が明記されています*3。
したがって、LGBTQに対する差別もセクハラに該当します。
介護事業者は、LGBTQ当事者である従業員がセクハラを受けないように、また万が一セクハラが行われた場合には迅速に対応できるように、適切な措置を講じなければなりません。
LGBTQに対する差別を防止するため、介護事業者が講ずべき措置
LGBTQに対する差別を防止するため、介護事業者が講ずべき具体的な措置としては、以下の例が挙げられます。各措置の詳細については、厚生労働省が公表しているセクハラ防止指針において示されています*4。
職場におけるセクハラを禁止する旨、およびセクハラをした者については厳正に対処する旨などを明確化し、従業員に対して周知・啓発することが求められます。
(2)セクハラに関する相談・対応体制の整備
ハラスメント相談窓口を設け、相談があった際には適切に対応できるように連携を準備するなど、平時から体制整備を行うことが求められます。
(3)セクハラ発生時の迅速かつ適切な対応
実際にセクハラが発生した際には、事実関係を迅速かつ正確に把握して、被害者への配慮・行為者に対する懲戒処分等・再発防止措置などの対応をとることが求められます。
(4)上記(1)~(3)と併せて講ずべき措置
セクハラに関する情報は、被害者や行為者などのプライバシーに属するため、プライバシー保護のための措置を講ずることが求められます。
また、セクハラに関する相談等をしたことを理由に解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、従業員に周知・啓発することが求められます。
LGBTQに対する差別を放置した介護事業者が受けるペナルティ
LGBTQ当事者の従業員に対する差別を放置した介護事業者は、厚生労働大臣から是正勧告を受けることがあります(男女雇用機会均等法29条1項)。
是正勧告に従わなかった場合は、厚生労働大臣による公表処分の対象となります(同法30条)。
公表処分がなされると、LGBTQに対する差別が横行している状況が世間に周知され、介護事業者としての評判が低下してしまう可能性が高いので要注意です。
まとめ
LGBTQ当事者である従業員への配慮は、近年特にその必要性が高まっています。
介護事業者においては、LGBT法や男女雇用機会均等法の内容を踏まえた上で、LGBTQの従業員に対するセクハラ等を防止するため、適切な措置を講じましょう。
*1正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」。
参考)e-gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC1000000068
*2正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。
参考)e-gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000113
*3参考)厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)【令和2年6月1日適用】」p1
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf
*4参考)厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)【令和2年6月1日適用】」p3~7
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf
阿部 由羅
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。
注力分野はベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続など。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
各種webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw