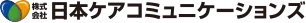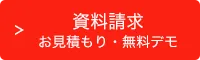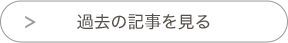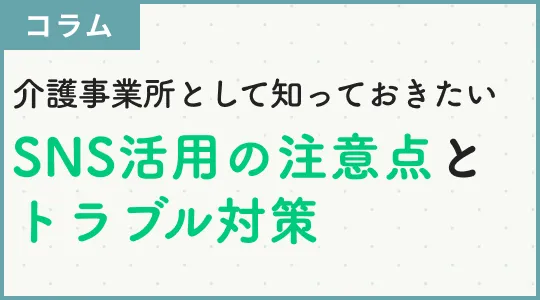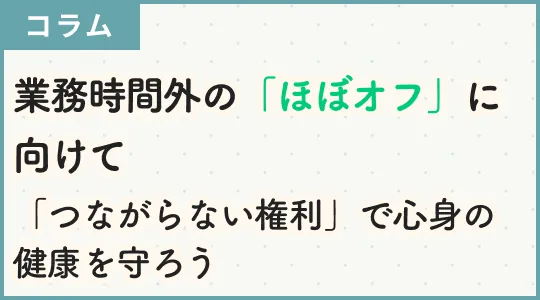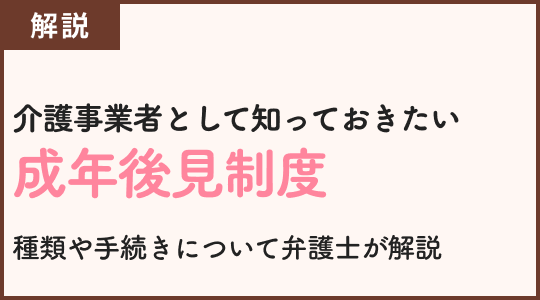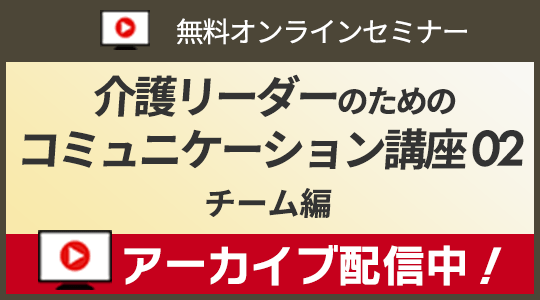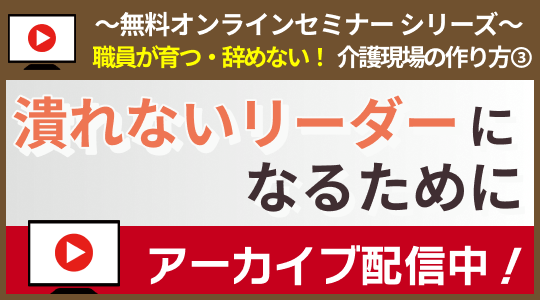高齢者の話を聞くのが好きだ。
特に女性の話は面白い。
そう思うようになったのは、小さなカルチャーセンターの和裁教室に通い始めてからだ。
その教室の存在は、インターネットで見つけた。よく、こんな時代に取り残されたような教室の情報が、ちゃんとネットに載っていたものだと思う。そう思ってしまうほど、そのカルチャーセンターは昭和だった。

カルチャーセンターよりも老人クラブと呼んだ方がふさわしい教室の中にあって、当時40歳を過ぎたばかりの私は飛び抜けて若かった。
なぜ私がそんな場違いとも言える場所に通い始めたかというと、祖母から譲り受けた着物の仕立て直しをしたかったから。正絹の訪問着であれば迷わずプロにお任せするのだが、直したいのは紬の普段着だったので、試しに自分で縫ってみたくなったのだ。
自宅から自転車で通える距離の和裁教室をパソコンで検索したところ、ヒットしたのはたったの2件で、そのうちの1件はプロの和裁師を目指す専門学校だった。
私は本格的に和裁を学びたいわけではなく、1枚の着物をちょっと縫ってみたいだけだ。厳しく指導されたいわけではないし、あまりお金もかけたくなかった。
そうなると、そのカルチャーセンターに行ってみるより他に選択肢がない。
見学に出向いた日、私がそろそろと教室の引き戸を開けると、窓際の明るい席で針を運んでいた上品そうなご婦人が振りむいて、あでやかに微笑んだ。
「まあまあ、お若いお嬢さん。よういらしたねぇ」
こちとらすでに「お若いお嬢さん」と呼んでいただけるような年齢ではなかったのだが、人生の大先輩であるご婦人にとっては、まだ十分に若く見えるのだろう。
「あの、すみません。お邪魔します…」
「どうぞどうぞ。ここへ来て、お座りなさいや」
手招きされて、私は通路を挟んだ隣の席へ腰を掛けた。
「ありがとうございます。あの、今日はここで和裁教室をやっていると聞いて、見学に来たのですが…」
「まあ、そうですか。今日はあいにく、私ひっとりしかおらんがですよ。いつもは、もう何人かおるがやけんどねぇ。先生は、今はお昼を食べにアパートへ帰ってますき、もう少し待ちよってくださいねぇ」
ご婦人がそう言い終わらないうちに、パタパタとスリッパの音を響かせて先生が階段を上がってきた。
「あぁ、わかちゃん、ごめ〜ん。待った?お昼に帰ったついでに、ちょっと用事をいくつか片付けてたのよ」
教室に飛び込んできた先生は、白髪のショートヘアがよく似合うきっぷのいい女性だった。
「先生、こちらのお嬢さんがねぇ、見学にいらしたと」
「あら、そう。見学といっても、今日はわかちゃんしか居ないし、寂しいわね。いつもはもうちょっと賑やかなのよ。たまにだけど、こんな日もあるの」
先生はそう仰ったけれど、まったく寂しくはなかった。2時間のレッスン中、お二人がずっとおしゃべりに花を咲かせていたので、十分にぎやかだったのだ。

「わかちゃん」と呼ばれた女性は、和華子さんという名前だった。
その日の和華子さんは、ウールの着物のアンサンブル(同じ生地を使って仕立てた着物と羽織のセット)に身を包んでいた。明るい黄色地に朱色と紺で格子模様が入った柄が若々しく、華やかな雰囲気の和華子さんにも、まだ寒いけれど春めいてきた季節にもよく似合っていた。
「お着物、素敵ですね。いつも和装でいらっしゃるのですか?」
「いえいえ、今はまだ寒いきね。私は寒い季節には着物で、暑い季節には洋服で過ごすがですよ。着物はぬくいし、何と言うたち帯がえいわね。お腹のまわりが温まるだけやのうて、無理に背筋を伸ばそうとせいでも、帯に体を預けちゅうだけでシャンとする。帯がコルセット代わりになるがよ。」
「わかちゃんはオシャレよね。私はもう、着物は着ていられない。どんどんほどいて、洋服にリメイクしちゃってるわ」。
「だって、先生。今のうちに私が着ちょかんともったいないろう?家には着物がぎょうさんあるけんど、娘も嫁も孫も、誰っちゃあ着んもの。 私が死ぬまでの間にできるだけ着いて、それで終わりよ。前は、死ぬ前にみな処分しちょかないかんと思うちょったけんど、今は故郷の町へ引っ越したきね。 今の家は海が近いき、捨てんとそのまま置いちょったって、南海トラフが来たら海が私と一緒に着物もぜーんぶサッパリ流してくれらぁね。やき、片付けるのは止めにしたが。 生きちゅうあいだに着たり、縫い直したりして、最後まで自分が楽しむことにしたがよ」
和華子さんはあっけらかんとそう言い放って、先生と二人して楽しそうに笑い合った。
和華子さんと先生は、場所は違えどそれぞれ太平洋に面した漁師町の生まれだそうだ。
先生は義務教育を終えると、一度は高知市内で就職をした。けれど、東京から巡業にきたファッションショーを一目見るなり強い衝撃を受け、農業を営んでいた両親を説得して上京。服飾専門学校で和裁と洋裁を学び、そのまま東京で生涯独身のままキャリアウーマンとして生きる道を選んだ。
東京で過ごした時間が長いためか、先生はまったく土佐弁を話そうとしない。
一方の和華子さんは、羽振りのいい網元の家に生まれた才媛だ。和華子さんの世代では、いくら頭が良くても女の子が進学校に入ることも、さらに大学へ進むことも、ましてや県外に出してもらえることも稀であったが、和華子さんは中学から県内トップの進学校に通い、関西地方にある名門大学の英文科へ進学している。
しかし、大学卒業後は高知に戻り、お見合いをして商家へ嫁いで、妻として夫と家を支えて生きてきたそうだ。
生き方は異なるが、先生と和華子さんは同世代で、漁師町で生まれ育ったことと、60歳を過ぎてから故郷に戻って家を建て、現在は気ままに一人暮らしをしていることが共通点らしかった。
「先生、先生」「わかちゃん、わかちゃん」と掛け合いながら、二人がおしゃべりに興じる姿はまるで女学生のようだ。
二人の口から語られる、昔の高知の漁村での暮らし、当時の人々の営み、繁華街の様子などは、郷土資料館に収められているような文書や写真よりも活き活きとして、その時代の風俗が目の前に浮かび上がってくるようだった。
二人の話を聞いているのが楽しかったので、私はその日のうちに入会を申し込んだ。
和裁教室は週に3日開催されており、自宅が遠方にある先生は、通勤が面倒だといういう理由で教室の近くにアパートを借りていた。週の半分はアパートで暮らし、残りの半分を家に戻って過ごすのだそうだ。
二重生活は不経済で、講師として得られる収入からアパート代を差し引けば、ほとんどお金は残らないように思えたが、もはや先生はお金が欲しくて働いていたわけではないのだろう。
和裁教室に在籍している生徒は20名ほど居たようだが、みなそれぞれのペースで通ってくるので、一度に集まるのは5人前後であることが多い。
先生は、特に指導らしい指導はしていなかった。最初に基本的な縫い方と糸の留め方だけを教えたら、あとは
「ここからここまでは並縫いね」
「ここは本返し縫いで」
「ここは耳ぐけにしましょう」
と簡単な指示を出すだけで、素人に難しい箇所は
「ちょっと貸して」
と縫いかけの着物を取り上げて、ささっと自分で仕上げてしまう。
「ちゃんと覚えたい人には教えるけど、ここへ来ている人のほとんどはそうじゃないから。
みんな、出かけるところがもう他に無いのよ。ここがあれば家から出るし、お街へ行くと思えばおしゃれをして化粧もするでしょ。来たらこうして人と顔を合わせるし、手も口も動かすからボケ防止になるじゃない。
私も、もうじき80歳になるからそろそろ辞めたいと思ってるんだけど、教室を閉めたらみんなの行き場が無くなっちゃう。だから、なかなか辞められないのよねぇ」
そう話す先生にとっても、ここは大切な居場所であり、こうして働くことが生き甲斐なのだろうと思えたが、もう目には限界が来ているらしく、針の穴に糸を通すことができなくなっていた。
和裁教室はいつも賑やかだった。おしゃべり好きで話し上手な和華子さんが来ている日は特に、他のみんなのおしゃべりも大いに弾んだものだ。
私は着物を縫いながら、幾人もの女性たちの人生の歩みに耳を傾けた。
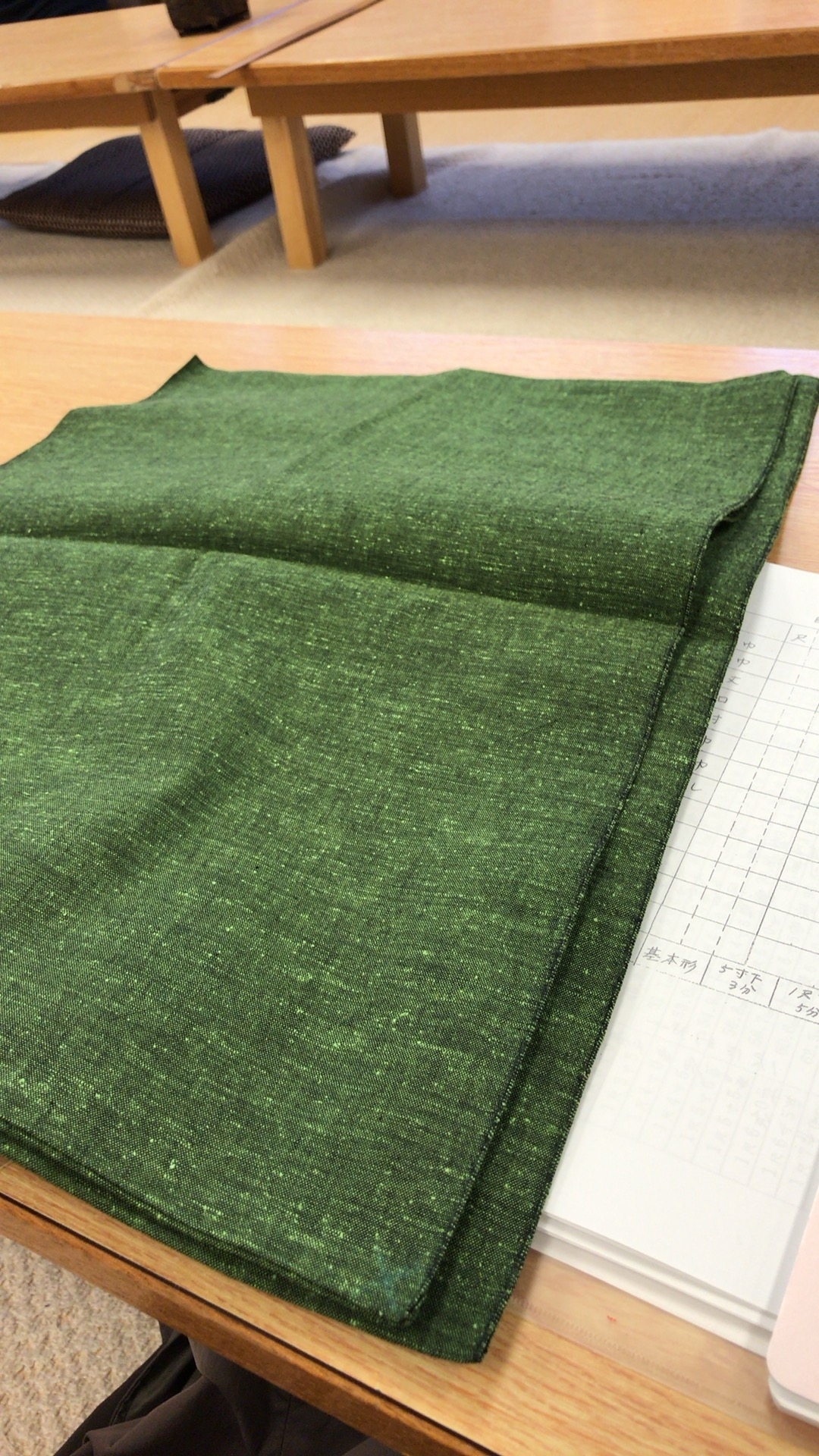
70年、80年と生きてきたご婦人たちが、自らの生涯を振り返る語り口はさらりとしていて、それでいて内容には奥行きがある。
こう言っては語弊があるかもしれないが、老人は若者とちがい、今この瞬間を生きていないからこそ、どんな話もドロドロとしておらず爽やかなのだ。幸も不幸も、激情も苦悩も、彼女たちにとって全ては過ぎ去った過去なのだから。
私は結局、その和裁教室に通っていた2年足らずの間に2枚の着物を縫い上げた。当初は1枚だけ縫ったらすぐに辞めるつもりだったのが、年配のご婦人方との交流が楽しくて、つい2枚目を縫い始めてしまったのだ。
それほど楽しく通っていた和裁教室だったが、2枚目の仕上げに入る頃には辞める決心がついていた。いつも場を盛り上げてくれていた、ムードメイカーの和華子さんが亡くなったためだ。
和華子さんは胃癌だった。
ずっとお元気だったので信じられなかったが、「最近ちょっと胃の調子が悪い」と言い出してから、あっという間にお亡くなりになってしまった。検査を受けて癌だと分かった時には、すでに手遅れだったのだ。
和華子さんが居なくなった教室は、火が消えたように静かになった。たまたまなのかもしれないが、和華子さんが居なくなってから、体の不調や家庭の事情で教室を辞める人が数名続き、先生も1番の話し相手だった和華子さんが居なくなってからは、急に張り合いを無くしたように見えた。
コロナが日本を襲ったのは、それから2年後のことだ。
後期高齢者ばかりのカルチャーセンターが、コロナの衝撃に耐えられるはずがない。先生方がどうなさっているのかと気になって、ネットを探した時にはもう、カルチャーセンターと教室の情報は削除されていた。
コロナがなければ、ひょっとして教室はまだ続いていたかもしれない。しかし、コロナがなかったとしても、やはり遠からず閉鎖することになっていただろう。きっと、良い機会だったのだ。
あの場所が無くなってしまったことは寂しかったが、和裁教室に通ったおかげで、私は「老い」をポジティブに捉えられるようになっていた。私は和華子さんのようにチャーミングな年齢の重ね方をしたいし、先生のようにいつまでもたくましく働いていたいと思う。
そうして70年、80年と生き抜いた後、ああして仲間たちと集いあって、「全ては遠い過去」だと笑い合うのは、きっと楽しいにちがいない。
マダムユキ
最高月間PV40万のブログ「Flat 9 〜マダムユキの部屋」管理人。

現場スタッフの視点から「信頼できる上司」の特徴、あり方について、筆者の実体験を基に紹介。
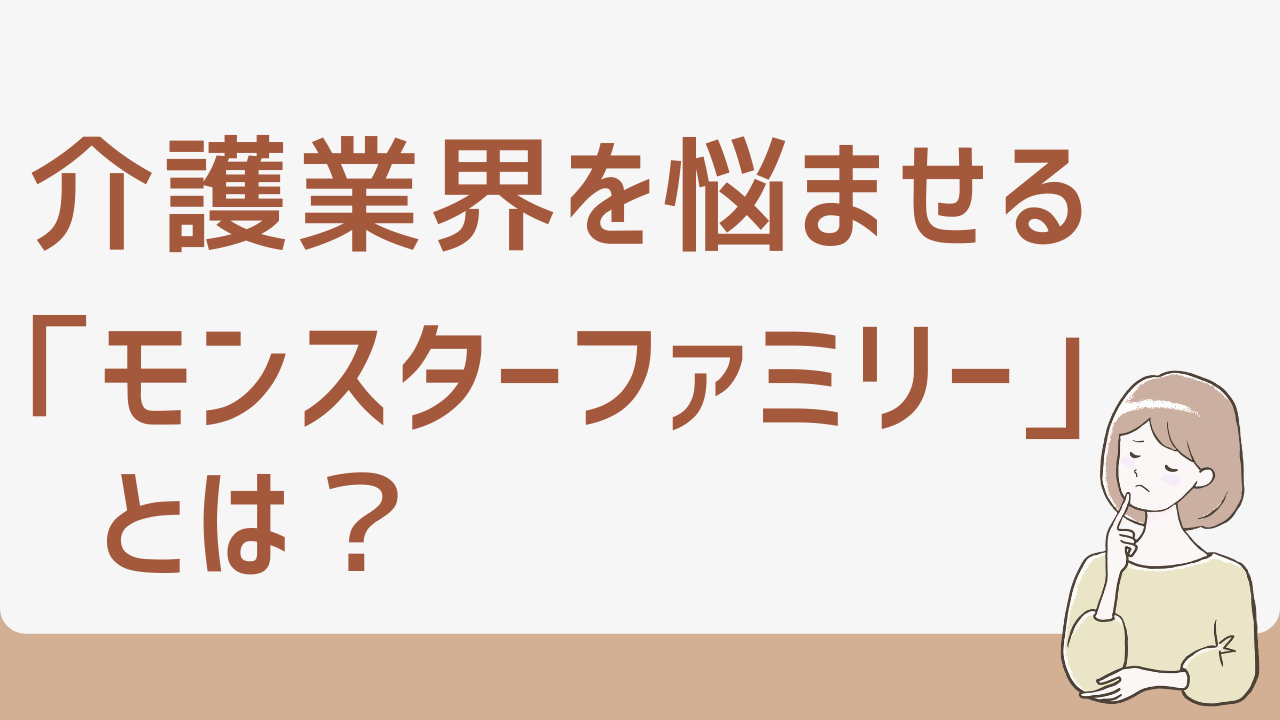
介護業界を悩ませる「モンスターファミリー」についてカスタマーサポートの観点から問題を大きくしない対応のポイントを紹介。

書店を舞台に居場所の大切さ、そこで生まれるコミュニケーションについて考えます。