
第6回は仕事に必要な「ヒトの課題」、高頭先生からのメッセージをお届けします。
create 現場における「ヒト」の課題
今回から「ヒト」の課題について数回取り上げます。
介護は、たとえロボットやICT化、DXが進んだとしても、労働集約型の産業であることには変わりない部分が残ると思われます。
やはり対人接客型サービスは、どこか人の手が必要になるからであり、小売店のセルフレジのようなわけにはいかない部分が残るからです。
またアセスメントやケアプランにAIの活用が普及したとしても、「AIに対して、適切な問いを投げる」スキルが重要であり、知識やスキルなしには、適切な問いを設定できることはありません。
他業種の実例ですが、サブスクリプションの退会防止のために、AIに対して、近々退会しそうな会員のリストを作るように命じました。もちろんAIには得意な作業です。
会社の幹部は、そのリストを元に、退会候補の会員に積極的な説得やアプローチを繰り広げました。その結果は、もちろん退会せずに継続する顧客もいましたが、やはり退会する顧客も多く、アプローチのためのコストが、バカになりませんでした。
実はこの場合の適切な「問い」は、「近々退会しそうだけれども、アプローチすれば継続の可能性が高い会員のリスト」、「会員タイプ別の継続に資するアプローチの仕方」などの問いの群だったのです。このような適切な問いを立てれば、いたずらなコスト増を避けることができたはずです。
このことから学べることは、AIにせよ、ロボットにせよ、ICT化にせよ、使いこなす人材の能力がカギとなるということです。
現状では、最初からそのような能力を持った人材を、事業所が採用できるかと言えば、正直非常に困難であろうと思われます。やはり、報酬面において、他業種と比較すれば、見劣りすることは否めないからです。
現状は単なる「人手不足」という認識が主流になっていますが、今後は「スキルを持った人が不足する」=「人材不足」の面が、表面に浮上してくると思われます。
現在でもITリテラシーの低さがICT化推進の妨げになっている事業所は多いようです。
・採用時点で能力のある人を採用することは難しい=社内でスキルを身につける必要がある
・しかし業務が忙しくて、ITにせよ、介護技術にせよ、学んでいる時間がない
・あるいは、研修や業務改善のための予算が取れない
などの要件により、悪循環に陥っていることを意味します。「ヒトの課題」とは、優秀な人が採用できないというものではなく、
・採用した人が辞めてしまう
・育たない、成長しない、一人前にならない
・新技術が入らない
・今時の介護の考え方を取り入れられない
・専門性が育たないなど
「人手から人材へ」の成長の仕組みがうまく回っていないことにあります。正直に言いまして、能力・スキルの不足を、長時間労働や人数の投入によって補うのは、効率が悪すぎます。悪循環を断ち切り、成長する人材の集団、学習する組織に変わっていく必要があるのです。
そのためには、何らかの痛みやコストが必要になりますが、今決断しなければいけない時期に来ているのです。なぜなら、LIFEの登場により、大きく介護の世界が変わろうとしているからです。
次回は、「ヒトの課題」その2として、人材育成、成長、学習の基本的な理解について解説いたします。
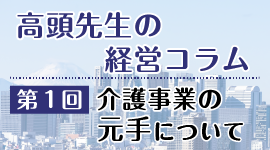
介護事業を開業する際に気をつけるべきこと 予め用意した「元手」はオーバーすることが多い、その理由とは
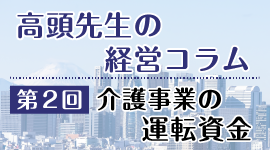
介護事業の開業直後、2か月分の運転資金じゃ足りない!? 運転資金が足りなくなるリスクとは
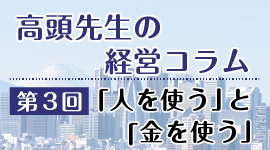
「人を使う」ことと「金を使う」ことの関連性や考え方について 事業を活性化させ、利益を生み出すには…?
1998年より、ケア管理システムをはじめ、介護保険関係のシステム開発を数々手掛ける。
介護施設への経営(介護福祉施設の稼働率向上、在宅サービスの利益向上)・ケア(利用者の健康向上、自立支援)のコンサルティング業務も数多く、講演活動も精力的に行なっている。
社会福祉法人虐待再発防止第三者委員を歴任。
近年は特に介護事業の人材定着、能力向上プロジェクトに注力している

『今日から使えるユニットリーダーの教科書』
『100の特養で成功!「日中おむつゼロ」の排せつケア』
『あなたを助ける 介護記録100%活かし方マニュアル ただ書くだけの記録から ケアを高める記録に』(以上メディカ出版)
『介護現場のクレーム・トラブル対応マニュアル』(ぱる出版)
『介護事業経営・運営のノウハウ:これで失敗しない!(共著 同友館)
『3ステップで目指せ一流 ホンモノの介護職になろう: ステップ1 駆け出し編 』
『3ステップで目指せ一流 ホンモノの介護職になろう: ステップ2 本物になろう編 』(339BOOKS: Kindle版)

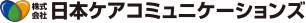

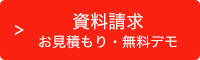



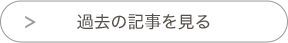
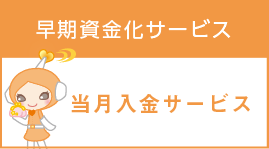
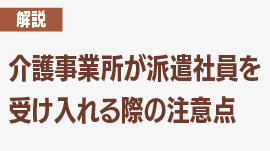
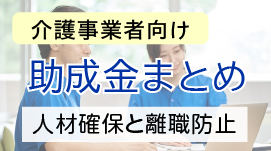
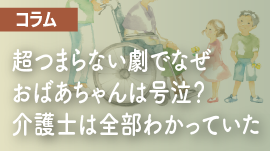


![[無料セミナー]原因別不穏への対応:見当識障害に起因する場合-「認知症ケアの実際」シリーズ⑦](https://www.care-com.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/thumbnail_sem202307_2arc.png)